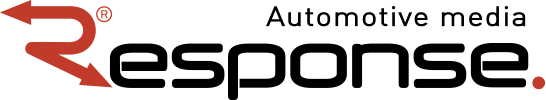自動車ジャーナリスト・自動車経済評論家である著者が、企業動向や国の政策などを紐解きながら自動車業界の現状と未来に迫る連載「池田直渡の着眼大局」。
前編では、トヨタのスーパー耐久シリーズにおける水素エンジンカローラの挑戦を振り返ると共に、水素内燃機関の仕組みや進化を解説した。後編では、レース活動のスタンスと今後の可能性、そこから繋がる商用車ビジネスの展望を分析する。
市販車開発のためのレース活動
トヨタにとってレース活動とは、「市販車の開発システム」の開発のためにある。次のレースまでどこをどうする。本戦の日程は動かせない。自分の都合で延期が不可能なそういう厳しい目標設定で開発を進める、つまりレースの鉄火場でのアジャイル開発のノウハウを貯めるためにレースに参戦している。だから、ここで難しいからと言って安易な道に逃げたらレースをやる意味がない。

ついでに簡単に説明しておくと、自動車メーカーにとってのレースは、基本広告の一環である。それも効果測定の定かならざる広告である。どちらかと言えば、レースをやりたい人がいて、ある種の方便として広告効果を訴えている。だから本業の利益が減るとあっけなく中止命令が出てしまう。やりたいという情熱は本物だろうが、だったらどうするという戦略がないからそうなるのだ。
おそらくトヨタの人たちも、本音を言えばレースをやりたいからやっているのだが、彼らは「やりたいから」だけでは続けられないことを熟知している。だから「レースをやると儲かる」仕組みを必死に作り上げた。それこそが「レース速度での開発手法」を開発する手段としてレースを活用することだ。
そのために、トヨタは24時間耐久レースに出場するに当たって、労働基準法を守っている。守っているのは労働基準法だけではない。部品の開発も全て市販車と同じ手順で行う。破損した部品を「いいから1mm径を上げとけ」などという勘と経験に依存した改良は許されない。どこでどういう負荷がかかって壊れたかを突き止め、その負荷に耐えるための強度計算をきちんとして、開発過程の全ての記録を残す。それらの書類のフォーマットは市販車と全く変わらない。だからトヨタがレース用に開発した部品は、道公法に抵触しない限りそのまま市販車に採用することができる。「レースだから特別」というやり方をしていては、開発手法の開発にならないからだ。
すべての条件を市販車開発同様に揃え、ピットスタッフはシフトを組み、時に労働組合と話し合いをして、全て法的、社会的、社内的規定を遵守してレースを戦っている。そうすることで、そのノウハウの全てがトヨタの本業にフィードバックされ、それこそがトヨタの開発力に直結するからこそ、トヨタはレースを絶対に止めない。というか止められないのだ。
「超電導モーター」が持つ可能性とは?
さて、そうして、この富士ラウンドで、液体水素をとりあえず使えるようになったが、システム重量をなんとかするのが次の課題である。そこでトヨタは、また驚くべきことを言い出した。超電導モーターである。

超電導とは何か? 多少乱暴を承知で言えば、ある種の金属は、極低温に冷やした時、電気抵抗がゼロになる。素材によってその温度は違うが、マイナス253度という液体水素の温度なら使える素材はいくつもある。
このシステムなら液体水素はタンク内にあるので、これを使って冷やしてやれば超電導状態を作り出せる。超電導状態では、常温では絶対不可能な細い線に大電流を流すことができる。ブースに展示されていた超電導用の導線は、紙のように薄い。にもかかわらず、従来の銅でできた直径5mm角ほどの線と同等の電流が流せるそうだ。

「超電導モーター」で検索してみると、その夢のような性能に驚くことになる。現在は全ての事例はラボレベルなので、出力10倍とか体積10分の1とかまさに夢の様な数字が散見される。例えば2022年6月23日に東芝から発表された超電導モーターは、航空機への利用が視野に入った2MWの大出力で、従来の同レベルのモーターに対して10分の1に軽量化・小型化されているという。つまり、超電導大出力モーターを作れば、あの巨大でゴツい液体水素用の燃料ポンプは圧倒的に軽く小さくなる見込みである。

トヨタの説明によれば、この超電動モーター燃料ポンプの投入は「年内は難しそう」とのこと。一刻も早く現物を見たいが、まだしばらく我慢というところ。来年の開幕戦には出てくる可能性が高い。
水素の商機は商用車に…CJPTの取り組み
さて、ではトヨタはこんな技術を開発して、どうしようとしているのだろうか? そこには開発手法だけでなく、実はトヨタのビジネスに直結する未来技術がある。