ドゥカティのアドベンチャーモデル「ムルティストラーダV4S」を楽しみながら、日本の美しさを再発見する。
そんな極上のひと時をサポートしてくれるプログラムが「Multistrada Discover Japan Trip」だ。西は岡山、北は北海道までカバーする本イベントを、レスポンスも体感。2泊3日の旅を通じて、大阪から名古屋に至る景色の変化を堪能した。
「ドゥカティ大阪イースト」を出発してムルティストラーダV4Sの優しさに触れる
ムルティストラーダは、初代モデルが2003年に登場している。2019年には累計生産台数10万台を突破するなど、ドゥカティのシェア拡大に大きく貢献。その最新モデルであるムルティストラーダV4Sは、ありとあらゆる部分が刷新され、2021年に日本へ導入された。
2003年当時、空冷2気筒だったエンジンは、これまでに目まぐるしく改良され、現在は937ccと1262ccの水冷2気筒、そして1158ccの水冷V型4気筒をラインナップ。新世代のV4エンジンを搭載したモデルはフラッグシップの役割を担い、その先進性と懐の深さにおいて、一歩抜きん出た存在と言える。
 ムルティストラーダV4Sと今回の旅人である大関さおりさん、伊丹孝裕さん
ムルティストラーダV4Sと今回の旅人である大関さおりさん、伊丹孝裕さん今回の旅は、大阪府東大阪市のディーラー「ドゥカティ大阪イースト」から始まる。大容量のサイドケースを持つ2台のムルティストラーダV4Sは、スリムさが特徴のドゥカティの中にあって異質な存在感を放つも、その印象はまたがった瞬間に解消される。ひと度、シートに身を預ければ足つき性に不安はなく、ライダーを優しく迎え入れてくれるからだ。
実は、その優しさにはもう一段階、上がある。ハンドル左側に備わるサスペンションマークのボタンを長押しすると、シート高をさらに下げることができるのだ。これは2022年モデルから採用された「ミニマムプリロード」と呼ばれる機能で、電子制御サスペンションの利を生かして、プリロード量を最弱状態で維持できるというもの。これによって、ライダーや荷物の重量が掛かった時のサスペンションの沈み込み量が増大し、結果的に足つき性と低重心化に貢献する仕組みだ。
 大阪の市街地を軽快に進むムルティストラーダV4Sと大関さおりさん
大阪の市街地を軽快に進むムルティストラーダV4Sと大関さおりさん
簡単な操作性も含め、この効果は大きい。足つき性のみならず、車体の引き起こしが容易になり、極低速走行時の一体感も向上。そもそもオールラウンドなキャラクターを謳ってきたこのシリーズの中でも、屈指のフレンドリーさを身につけたことを意味する。
 ストップ&ゴーを繰り返しても扱いやすいムルティストラーダV4S
ストップ&ゴーを繰り返しても扱いやすいムルティストラーダV4Sミニマムプリロードの恩恵は、走り始めてすぐに体感することができた。日中の大阪は当然交通量が多い。市街地であっても自動車専用道路であってもしばしば渋滞に遭遇し、ストップ&ゴーを繰り返すことになる。
 メーター画面中央に「Min」が表示され、シート高を下げるミニマムプリロードが動作している
メーター画面中央に「Min」が表示され、シート高を下げるミニマムプリロードが動作しているしかしながら、足の上げ下げにストレスはなく、極めてフレキシブルな出力特性も手伝って、渋滞も難なくクリア。阪神高速13号線を経由し、大阪城の天守閣を右手に眺めながら最初に向かった先は、通称「裏七岸(ウラナナガン)」と呼ばれる撮影スポットだ。
ウラナナガン、舞洲、大阪城、道頓堀、様々な顔を見せるなにわの街
 全長980m、世界第3位の長さを誇るトラス橋
全長980m、世界第3位の長さを誇るトラス橋ここは天保山運河と南港を結ぶ港大橋のたもとに位置し、その橋脚を眼前に見上げられることで密かな人気を集めている。大小と長短が入り混じった鉄鋼材がトラス状に組み合わせられ、巨大な構造体を形成。980mに及ぶ全長は、トラス橋としては世界第3位の長さを誇り、半世紀近くに渡って、大阪の交通網を支えている。赤の色合いといい、いかにも頑強そうな部材といい、ムルティストラーダV4Sのシートフレームとの親和性が感じられるポイントだ。
 全長980m、世界第3位の長さを誇るトラス橋
全長980m、世界第3位の長さを誇るトラス橋港大橋を後にし、天保山観覧車とユニバーサルスタジオジャパンを横目に見つつ、湾岸線を北上する。海からの風と匂いを身体で感じ、エンジンが発するまろやかな鼓動感に包まれながら舞洲方面へと車体を向けた。
 湾岸地域のコンテナヤードを進む
湾岸地域のコンテナヤードを進むここは廃棄物の処理を目的に造成された人口島だ。70年代から埋め立てが始まり、1991年に舞洲という愛称が決定。現在は緑地公園やスポーツ施設、物流センターも整えられ、レジャーにおいてもビジネスにおいても重要な役割を果たしている。
 大阪市建設局舞洲スラッジセンター
大阪市建設局舞洲スラッジセンター舞洲へは此花大橋から入り、常吉大橋から出るルートを選んだのだが、どこを走っても目に入る建物が、大阪市建設局舞洲スラッジセンターだろう。いわゆる下水処理場ながら、メルヘンにもサイケデリックにも見える外観が話題を呼び、舞洲地区のランドマーク、あるいはシンボルになっている。
この施設はオーストリアの建築家、フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサー氏がデザインを手掛け、2004年に第1期事業が完成した。青い煙突によって大阪の空と海、その頂上に設けられた黄金色のキューポラによって未来への夢と希望を表現。外壁を彩る赤いストライプは、汚泥を処理する炎がモチーフになっているという。敷地内には遊歩道が整えられ、見学可能な施設もあるため、立ち寄ってみるといいだろう。
 大阪城とムルティストラーダV4S
大阪城とムルティストラーダV4Sそうやって大阪の海沿いを楽しんだ後は、再び市内へ戻ることにした。大阪城から道頓堀へ至る、これ以上ないほどの王道ルートを選択し、ザ・大阪といった風情を満喫。戎橋とグリコのネオンサインを臨む場所は、渋谷のスクランブル交差点と並ぶ都心部の象徴に違いなく、これを大阪最後のワンカットとした。
 戎橋とグリコのネオンサイン大阪を象徴する風景だろう
戎橋とグリコのネオンサイン大阪を象徴する風景だろうさて、そうこうしている内に、すっかり日が暮れていた。普通の旅行や観光ならここで1日目を終えてもいいのだが、ムルティストラーダV4Sに乗る身としては距離的にやや物足りないところ。そこで、同じ関西でも趣が真逆と言えるほど異なる、京都へと足をのばすことにした。
 道頓堀2丁目商店街への入り口
道頓堀2丁目商店街への入り口京都の街並みにも似合うイタリアンレッド
阪神高速から第2京阪へと乗り入れ、そのまま一気に京都へ。人通りが少なくなった静寂の中、清水寺へ向かう参道のひとつである二寧坂を散策した。二寧坂には、幕末の動乱を今に伝える霊山歴史館や、大正時代の画家にして詩人である竹久夢二の石碑といった史跡がある一方、数寄屋建築の風合いを生かした新しいコンセプトのスターバックスが違和感なく融合。新と旧、和と洋が折り重なる中、あらゆる要素を併せ持つムルティストラーダV4Sの存在が映えた。
 京都の清水寺へ向かう参道のひとつである二寧坂
京都の清水寺へ向かう参道のひとつである二寧坂走っては止まり、止まっては撮るという一日を苦もなくこなしてくれたムルティストラーダV4S。通常、こうしたキャラクターのモデルは、ひと度走り出せば可能な限り距離を稼ぎたくなるものだが、快適で我慢を強いられることのないライディングポジションが停車をためらわせない。明日からの風景に思いを馳せつつ、一日目の旅を終えた。
Multistrada Discover Japan Trip特集ページはこちら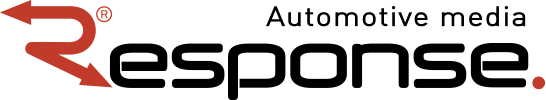




































![[15秒でわかる]ドゥカティ『モンスター・セナ』…世界限定販売、アイルトンを称える](/imgs/sq_m_l1/2010382.jpg)









