2022年5月、JR東日本はSuicaを利用した際に記録されるデータを匿名化し、統計的に処理した結果をレポートとして提供する「駅カルテ」の発売を開始した。旅客サービスを通じて得られた人流データを活用することで、「駅から駅までの移動」以外の価値を創造することに成功したといっても過言ではないだろう。
交通系ICカードを利用したデータビジネス
Suicaのデータを分析すれば、その駅で降りた人がどの駅から電車に乗ったのかがわかる。時間帯別、性別、年代別に集計することも可能だ。
例えば、A駅の近くに野球場があるとして、試合の開催前の時間帯にA駅で下車した人を分析すれば、野球を見に来た人の入場駅を推定できる。さすれば、試合がある日には、その入場駅でA駅周辺の混雑が予想されることなどを告知し、早めの来場を呼びかけることで混雑を緩和できるかもしれない。乗換駅に野球場までの乗換案内を掲示することで、乗客の利便性を高めることも一考である。
観光地を擁する自治体であれば、乗降客数が多い駅でありながら、その観光地に来る人が少ない駅を特定し、広告を打つことで、新規の集客を効率的に増やすことが考えられる。公共交通機関の利用を促すため、入場駅からの運賃や移動時間を明示することも有効であろう。
当面は、駅での乗降に関する人流データのみを対象としているが、店舗での商品の購入やバスでの移動などのデータも蓄積されている。将来的には、その観光地に来た人がどの駅から来たのかだけではなく、どの土産物屋で何を買ったのか、何時間くらい滞在したのか、帰りにどこで食事をしたのかといったことまで分析できるようになるかもしれない。JR東日本は、社内にあったビッグデータを加工し、マーケティングの高度化に資するツールとすることで、新たな収益機会を獲得しつつあるのである。
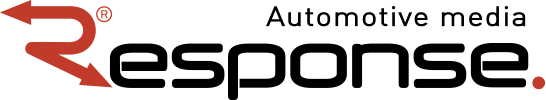








![このクルマ大丈夫? トヨタ・ホンダなども型式指定で「不適切事案」内部調査で発覚[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_l1/2013143.jpg)







