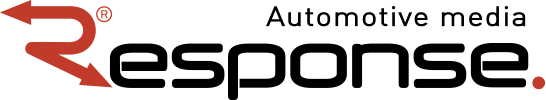72年に発表された初代E12型以降、現在までの販売台数は1000万台を超えるというBMWの収益的な大黒柱といえば『5シリーズ』。昨今は先進国市場を中心にセダン退潮の兆しがみられるが、BMWのエンジニアは自らのクルマづくりのど真ん中として、3・5・7シリーズに軸足を置くことにまったく変わりはないと意気軒昂だ。
先日登場した新型メルセデスベンツ『Eクラス』の試乗会でも、開発担当役員は同じようなことを口にしていた。恐らくはアウディも含めたジャーマンスリーにとって、この牙城は自らのアイデンティティとして可能な限り死守すべきものと考えられているのだろう。
 BMW i5 eDrive40
BMW i5 eDrive408代目となるG60型5シリーズの最大のトピックは、昨年フルモデルチェンジとなったG70型『7シリーズ』と歩を合わせるように同一車台でBEV化を果たしたことだ。BMWの後輪駆動車全般が用いるクラスターアーキテクチャー=CLARと呼ばれる骨格は最新世代へと更新されており、7シリーズとの共通項も多い。
メルセデスは既にEクラスと『Sクラス』に該当するBEVを専用設計のプラットファームで販売しているが、BMWはCLARで内燃機側との互換性を確保して移行の流動性に対処している。各々に長所・短所があるがそれは後に触れようと思う。
◆かつての7シリーズを超えたサイズのボディに、最新OSを搭載
 BMW i5 eDrive40
BMW i5 eDrive40
新型5シリーズの車格は全長5060×全幅1900×全高1515mm。遂にEセグメントにして5mの大台を超えてしまった。ちなみに2~3世代前の7シリーズにほぼ同じといえば、その質量感はわかりやすいかもしれない。全高がやや高めになっているのはBEVを前提とした床面構成と居住性とのバランスを取るためで、外観上はその厚みを意識させないように車体下部を大胆にブラックアウトしている。この視覚効果もあって、見た目の印象的には7シリーズのような重厚さは感じない。Cd値は0.23とクラストップレベルをマークする。
本国仕様のパワートレインのバリエーションは6種類。2リットル4気筒ガソリンとディーゼル、2リットル4気筒と3リットル6気筒のPHEV、シングルモーターRRとツインモーター4WDのBEVとなる。うち、日本仕様として導入が決定しているのはガソリンとディーゼル、2種類のBEVとなる。19.4kWhのバッテリーを搭載し、WLTP値で100km前後のBEV航続距離を実現したPHEVは需要の多い欧州市場に振り向けるということなのだろうか、当面日本向けの導入はなさそうだ。
 BMW i5 M60 xDrive
BMW i5 M60 xDrive新型5シリーズの大きな特徴は、最新のオペレーティングシステムの搭載だろう。従来「iDrive8」と呼ばれていたそれは、BMW OS 8.5となり、インターフェース的にはタッチパネルでの利便性をより高めたグラフィックレイアウトや階層設定が特徴だ。社外アプリケーションとの親和性も織り込まれるほか、手持ちのガジェットとのミラーリンクを強化するなど、デジタルサービスのハブとなることにも配慮されている。ソフトウェア・ディファインドは自動運転時代も見据えた今日のクルマの主要ファクターとして捉えられつつあるが、BMWはこの柔軟性の高いOSを今後は他のモデルにも展開する予定だ。
◆旧『M5』も真っ青のパフォーマンスの「i5 M60」
今回の試乗で用意されたモデルは「i5 eDrive40」と「i5 M60 xDrive」の2台、つまり『i5』のみだった。ジャーマンスリーの中でみても、BMWは内燃機の共存を長期的視野でみている方だと思うが、それでもこの割り切りというところに、時流の凄みを感じてしまう。
 BMW i5 M60 xDrive
BMW i5 M60 xDriveところが、そのi5、ともあれパワートレインの出来が素晴らしかった。素性としてはゼロスタートからトルクが最大値に達するBEVの場合、人間の生理的にみれば特異なその力感をいかに人肌感覚になましていくかという点において、ドライバーやタイヤや路面といった流動的なパラメータを相手に繊細なノウハウが問われるところがある。中には開き直ってその特異さを際立てる味付けをするところもあるが、ドライバーが求める要件が特殊なスポーツカーでもない限り、それは本筋ではないと個人的には思う。
この点において、実はよりお見事だったのはMパフォーマンス扱いとなるM60の側だった。グレード名が示す通り、0-100km/hで3.8秒と旧『M5』も真っ青のパフォーマンスを発揮する源泉は、前261psの後ろ340psというモーターのパフォーマンスに由来するものだが、その火勢をまったく感じさせないほど、発進から極低速域、そして50km/h前後の常速域に至るまでのリニアリティが抜群に優れている。
 BMW i7 M70
BMW i7 M70そしてつけ加えればこの点、同時に試乗した『i7 M70』の側が更に強烈で、10km/h以下どころか3~4km/hの歩むような速度までスロットルのコントロールによる定常走行を坂道でもしっかりと受け付けてくれることに驚かされた。変速機や伝達系を噛ませたアナログな内燃機をどこまでダイレクトに意のままにアウトプットするかにことさら腐心してきただろう、BMWの積み上げてきたノウハウやプライドがきっちりモーターに宿っている。
シャシーの味付けも上手い。重心が低くなるとはいえ、まず車重的は動的性能を確保することが難しいはずだが、ランフラットタイヤのたわみの小ささを活かして四輪操舵を積極的に旋回の側に加勢させながら、乗り心地の側も先代を上回るしなやかなフットワークを得ている。試乗車はアクティブスタビライザーや後軸のエアサスなどオプションの電子制御アイテムが満載されていたが、これらが速度域を問わず違和感なく連携している辺りはさすがだなと思わされた。
◆なにをBMWらしさとして訴えるのか
 BMW i5 M60 xDrive
BMW i5 M60 xDriveというわけでi5を通して経験した5シリーズは、総じてBMWのBEVにまつわる知見の豊かさが伝わってくる仕上がりだった。が、何かが物足りないと思ったのも確かだ。振り返ってみると、それはBMWに乗ったという明快なインプレッションだと思う。
昨今のBMWが『iX』や『XM』、7シリーズなどで次々と新しいアプローチをみせている内装デザインは、さもすればBEV時代に考えられうるこの課題を補う目的があるのかもしれない。内燃機の放つ個性に頼れなくなった時代に、なにをBMWらしさとして訴えるのか。そのために大胆に光り物を配したオーナメントやラウンジソファのようなシートなど、自らの殻を破るための挑戦も必要という判断が現在のBMWの意匠に宿っているのだろう。
新しい5シリーズからは、いよいよ電化への端境期を迎えようという彼らの気構えがみてとれる、そんな気がした。
 BMW i5 eDrive40
BMW i5 eDrive40■5つ星評価
パッケージング:★★★★
インテリア/居住性:★★★★
パワーソース:★★★★★
フットワーク:★★★★★
おすすめ度:★★★★
渡辺敏史|自動車ジャーナリスト
1967年福岡生まれ。自動車雑誌やバイク雑誌の編集に携わった後、フリーランスとして独立。専門誌、ウェブを問わず、様々な視点からクルマの魅力を発信し続ける。著書に『カーなべ』(CG BOOK・上下巻)