来たる10月20日、オンラインセミナー【Season2】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.5 「テスラの事業戦略」を大研究 が開催される。
セミナーに登壇するのは、関西大学商学部教授の佐伯靖雄氏。テスラの事業戦略を経営機能ごとに分析し、その競争優位の源泉を明らかにするセミナーとなる。
セミナー当日はQAセッションも設けられ、モデレーターのナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリストの中西孝樹氏とともに、リスナーを巻き込んだ専門的なディスカッションに参加できる機会となる。セミナーの詳細・申し込みはこちらから。
佐伯教授にセミナーの見どころを聞いた。
■秀逸な自動車産業への参入手法
テスラの事業戦略を研究する佐伯教授は、テスラがいかに自動車業界への参入を果たしたのか、その手法が非常に秀逸だったと指摘する。
「この会社の強みは色々ありますが、私が個人的にこの会社を分析して最も優れていると思うのは、秀逸な市場参入方法にあったと感じています。一言で言うと、経営に関わる巨額の固定費、様々な固定費を全て変動費化することで、自動車産業という古くて巨大で、そして非常に高い参入障壁のある業界への参入を、非常にスムーズに成し遂げたということです。
生産面では、例えば初代ロードスターでは、ほとんどのハードウェアは購入品でした。自社で工場を建てたり、大規模な製造機械を買ったり、多くの人を雇って工場を建てることをせず、ほとんど外注で済ませました。」
「開発でも、シミュレーション技術を多用し、コストの高い試作車の製作を控えました。また、シミュレーションを使うことで非常に早いサイクルでの問題解決を可能にし、開発のコストを抑えることにも成功したと言えます。
さらに販売面です。ディーラーを持たず、基本的にインターネットのみで販売しました。また、初期はマーケティング面からプレミアムセグメントに特化しました。ガソリン車と同じような車で市場を代替しようとした日産のリーフとは、明らかに異なるアプローチです。」
「こういったすべての要素が、特に初期のテスラの成長を支えたと思います。」
■既製品流用から垂直統合へ
最初こそ既製品の流用から始まったテスラだが、近年のテスラを特徴づけるキーワードとして、佐伯教授は垂直統合を挙げる。
「テスラは、初期に販売したロードスターこそすべてのハードウェアを外注で済ませましたが、世代が新しくなるにしたがって車体や電池を自社で作るようになります。
現在主流となっている第三世代までは、アメリカではパナソニックと合弁してギガファクトリー1で電池を作っていますし、次の製品となる第4世代、4680という一番新しい電池に関しては、自社で内製も進めていますので、どんどん垂直統合を高めていっていると言えます。この垂直統合というのが一つ、このテスラの競争優位を考えるときのキーワードになっています。」
「2021年以降、特にここ2、3年はテスラに限らず自動車業界は非常に厳しい経営環境が続いています。
そんな中でも、テスラ単体は非常に良い業績を残してきて成長も止まっていないという状況なのですが、その背景にあったのは以下の3つのポイントだと思っております。
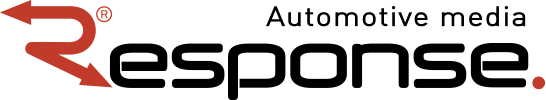
![「テスラの事業戦略」を大研究 – 関西大学 佐伯靖雄教授[インタビュー]](/imgs/p/hZgYd07SyqGxXeKSdNx7_YRJ30T7QkNERUZH/1942226.jpg)
![「テスラの事業戦略」を大研究 – 関西大学 佐伯靖雄教授[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/1942226.jpg)






![モビリティ業界の新規事業で常に意識する2つのこと…ヤマハ発動機 執行役員 青田元氏[インタビュー]](/imgs/sq_l1/2013438.jpg)



![[15秒でわかる]テスラ社名変更…電気自動車だけでなくエネルギー事業も](/imgs/sq_m_l1/2012064.jpg)
